
悲しいかな「おかだまくらりゅう」何て読まれたり「何なんだこれは」と意味を聞かれたりで、なかなか粋も洒落も伝わらないので、野暮な話『岡田枕流。企て1000年。』の意味・由来、そして意図を一挙解説しときますー。ゲゲゲ。自画自賛、傲慢、お馬鹿、身の程知らず、名前負け、と言われても由来だけは凄いっす。流石っす!
そもそも話は【漱石枕流(そうせきちんりゅう)】から始ります。中国西晋(せいしん)の孫楚(そんそ)は「石に枕し流れに漱(くちすすぐ)」と言うべきところを「石に漱ぎ流れに枕す」と言ってしまい、その誤りを指摘されると「石に漱ぐのは歯を磨くため、流れに枕するのは耳を洗うためだ」と言って無理くりごまかしたという故事で、へ理屈、偏屈者をある意味、賛美する洒落なのです。それが、みなさん多用される【流石(さすが)】の由来になったのです。「さすが!」のルーツですね。
その洒落に飛びついたのが造語と当て字、言葉遊びの洒落モン文豪 (本名)夏目金之助。その偏屈者を賛美するへそ曲がりのへそ曲がりの洒落っ気が大いに気に入り自身の筆名(ペンネーム)に即採用。【夏目漱石(なつめそうせき)】としたんであります。我々が漱石、漱石、と読んでいる呼んでいるのはある意味「流石(さすが)」「流石(さすが)」と言っている事なのです。「なつめさすが!」と。
そして、そんなイカしたネタを見逃すはずがありません。かの美食の偏屈王【北小路魯山人(きたおおじろさんじん)】は。黙っちゃいなかったんであります。時ちょうど、魯山人が鴨料理で名高いフランスのトゥール・ダルジャンを訪れた時の逸話、持参したわさび醤油で食したという武勇伝は誰もが知るところですが、その西洋料理視察の外遊から戻り、カトラリー(ナイフやフォーク)を休めるカトラリーレストにヒントを得て、それまで京料理の伝統には無かった箸枕(箸置き)を発案。自身の美食倶楽部「星ヶ岡茶寮」で箸休めの名脇役を作り上げたのが写真の「枕流」と記された箸枕(箸置き)なんでありまする。
ま。めぐりめぐってズーズーしくも品も格も幕下序二段くらいな鼻たれ小僧が、そんな遊びの極道さんたちに憧れて大胆にも使用させて頂いたのが【岡田枕流。(おかだちんりゅう)】ってワケです。くどいのが真骨頂の僕としては、それに加えて「企て1000年。」としたわけです。その意図は、そもそも建築を生業とする身としての心構え。6000年来のピラミッドに始まり、コロッセイム、万里の頂上、東大寺の大仏殿と、先人の都市造営、建造の足跡を知るに、まさに1000年後に残しうる思念と匠で建立される人類の文化を目の当たりにして、志を高く戒めとして自身を叱咤する標語、自是としたわけです。名前負け・位(くらい)負けする事なく極道を邁進する所存なり。ちゃんちゃん。なのでしたぁー。







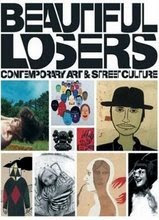
































5 件のコメント:
replica bags qatar great site a7o58t1g41 replica bags canada her comment is here t3a95u2e24 replica bags from china replica bags manila click this over here now u2f61z5g88 gucci replica handbags replica bags wholesale in divisoria v7s53i1u63
birkin bag
cheap jordans
yeezy supply
golden goose francy
supreme clothing
c9c59s9e74 u0h65a6m37 g9p94d7w82 p5e69g8m55 k1j22a3k93 o6m46l1c60
curry 6 shoes
palm angels
off white jordan
off white outlet
golden goose
a bathing ape
bape official
supreme
fear of god
jordan sneakers
suuoweei023
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
コメントを投稿